老後資金の形成手段として定着しつつあるiDeCo(個人型確定拠出年金)。2025年からこの制度が大きく改正され、加入対象者や掛金上限、そして出口戦略に影響を及ぼす税制変更が予定されています。
これまでiDeCoを活用してきた人にとっても、これから始めようと考えている人にとっても、「どう変わるのか?」「何に注意すべきか?」を正しく理解することが重要です。
とくに今回の改正では、掛金の上限が引き上げられるなどの“改善点”が注目される一方で、退職金と重なる「出口戦略」では“改悪”とも取れる税制変更が含まれています。つまり、使い方を間違えれば節税どころか税負担が増えるリスクもあるのです。
本記事では、2025年以降に予定されているiDeCo制度改正の内容を、制度の背景・改善点・注意点・対策という順序で詳しく解説します。これからiDeCoを活用したい方はもちろん、すでに拠出をしている方にとっても役立つ情報をまとめています。
iDeCoのおさらい|節税効果はどう働く?
iDeCoのおさらい
iDeCoは、自分で老後資金をつくるための制度であり、最大の魅力は「税金が安くなること」です。具体的には、以下の3つのタイミングで節税効果があります。
まずひとつ目は、「掛金が全額、所得控除になる」こと。たとえば、年収500万円の会社員がiDeCoで月2万円(年24万円)を積み立てた場合、その24万円がまるごと課税対象から外れます。
この人の課税所得は、おおよそ223万円(各種控除後)ですが、iDeCoの24万円を引くと199万円になります。これにより、所得税が約12,000円減り、住民税も約24,000円軽くなります。合計で年間約36,000円の節税になるというわけです。
ふたつ目は、運用中に得られる利益に税金がかからないこと。通常、株や投資信託で利益が出た場合、20.315%の税金が引かれますが、iDeCoではそれが非課税になります。たとえば10万円の利益が出た場合、通常なら2万円引かれるところを、そのまま10万円まるごと資産にできます。
そして三つ目が、将来受け取るときの控除です。iDeCoは60歳以降に受け取れますが、一時金でまとめて受け取るなら「退職所得控除」、年金形式なら「公的年金等控除」が使え、このときも税負担を軽くする仕組みが整っています。
このようにiDeCoは、「掛けるとき」「増やすとき」「受け取るとき」すべてにおいて節税メリットがあります。毎月の積み立てがそのまま節税につながり、将来の資産形成も同時にできるという、非常に優れた制度です。税金を抑えながらコツコツと老後資金を準備したい方にとって、iDeCoはとても心強い選択肢といえるでしょう。
iDeCoをお勧めできる人、できない人
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を自分で積み立てる制度で、節税効果が大きい点が魅力です。お勧めできるのは、長期間積立が可能で安定収入がある人、特に所得税・住民税を支払っている会社員や自営業者です。毎年の掛金が所得控除され、運用益も非課税、受取時も控除が使えるため、税制メリットが大きくなります。
一方、お勧めしにくいのは、収入が少なく所得控除の恩恵をあまり受けられない人や、60歳まで資金を引き出せない制約がネックになる人です。たとえば、サイドFIRE後で収入が200万円程度の場合、節税メリットが小さく、他の柔軟な資産運用手段を選んだ方がよいケースもあります。iDeCoは長期の資金拘束を前提とするため、自身のライフプランに応じた判断が重要です。
iDeCo改正の背景と目的とは
iDeCoは、将来の年金制度への不安や、老後資金の自助努力を支援するために設けられた私的年金制度です。掛金が全額所得控除となるほか、運用益も非課税、受け取り時には退職所得控除や公的年金等控除が使えるなど、税制優遇が魅力です。
しかし、現行制度には以下のような課題がありました。
- 自営業者と会社員で掛金上限に大きな差がある
- 加入可能年齢が早期に終了してしまう(多くは65歳未満)
- 企業型DCと併用しにくい構造
- 退職金との重複による「控除枠の衝突」問題
これらの問題を解決するため、政府は2023年末の税制改正大綱をもとに、2025年から段階的な制度見直しを進めています。
特にポイントとなるのは次の3つです。
- 掛金上限の大幅な引き上げ
- 加入可能年齢の延長(70歳未満まで)
- 退職所得控除に関する「10年ルール」導入による出口戦略の見直し
このように、iDeCo制度はより柔軟かつ実用的な形に進化しつつある反面、制度を正しく理解しなければ“損をしてしまうリスク”も高まっています。だからこそ、改正の背景と目的を押さえたうえで、改正内容を1つずつ整理していくことが大切です。
掛金・加入年齢の変更点まとめ
2025年のiDeCo制度改正では、掛金と加入年齢に関して大きな変更が行われます。これまで制度の制限によって活用しにくかった層にも広く門戸が開かれ、より柔軟に老後資産を築けるようになるのがポイントです。
まず、掛金の上限が大きく見直されます。第1号被保険者(自営業やフリーランスなど)は月額6.8万円から7.5万円へと拡大。第2号被保険者(会社員や公務員など)では、企業年金の有無にかかわらず、iDeCoと企業型DCの合計で最大6.2万円まで拠出可能になります。これにより、これまで月2万円程度しか掛金を出せなかった会社員も、大幅な拠出増が可能となります。

さらに、加入可能年齢もこれまでの「65歳未満」から、「70歳未満」まで拡大される予定です。現役で長く働く人が増えている現代において、この改正は非常に合理的なものといえるでしょう。再雇用制度などを利用して60代以降も収入がある場合、節税メリットを活かしながら資産形成を継続できるのは大きな魅力です。
このように、掛金や加入年齢の見直しは、多様なライフスタイルに対応する「使いやすいiDeCo」への大きな一歩となります。
退職控除「10年ルール」に注意
一方で、iDeCo改正の中で注意を要するのが「出口戦略」に関する変更です。特に大きな影響があるのが、退職所得控除に関する新たなルールです。
これまで、iDeCoの一時金と会社の退職金を「5年以上の間隔」で受け取れば、それぞれに対して別々の退職所得控除が適用できました。これを活用することで、両方を非課税または軽減課税で受け取ることが可能でした。
しかし、2026年からはこのルールが「10年」に変更される予定です。つまり、iDeCoを60歳で一時金として受け取った場合、会社の退職金は70歳以降でないと控除枠が分離されないということになります。これは多くの会社員にとって、非常に高いハードルです。
仮に60歳でiDeCo、65歳で退職金を受け取ると、控除枠が重複してしまい、課税対象額が増加します。退職金やiDeCoの一時金は金額が大きくなりやすいため、税負担も数十万円単位で変わる可能性があり、注意が必要です。
受取戦略で損しないための対策
今回の出口戦略の見直しにより、今後は「受け取り方の選択」が非常に重要になります。以下のような方法で、税負担を抑える対策が可能です。
● 一時金での受取を避け、年金方式にする
iDeCoは「年金」として分割で受け取ることも可能です。年金方式では退職所得控除ではなく、公的年金等控除が適用されるため、「10年ルール」の影響を回避できます。
● 一部を年金・一部を一時金に分けて受け取る
受取金額を分散し、課税所得の集中を避けることで、控除枠を無駄なく活用できます。
● 受取時期を10年以上空ける
現実的には難しいですが、60歳でiDeCoを受け取り、70歳以降に退職金を受け取ることで、従来どおりの控除分離が可能です。
特に年金方式の活用は、計画的に設計すれば税負担の軽減効果が高く、今後主流となる可能性もあります。制度が拡充されることで受け取りの選択肢も広がるため、老後のライフプランを見据えた戦略が重要です。
まとめ|制度改正で何が変わる?
2025年からのiDeCo制度改正では、加入者にとって大きなメリットがある一方で、新たな課題も生まれています。掛金の拡大や加入年齢の延長は、誰もが長く資産形成できる社会への前向きな一歩です。しかし、受け取り方次第では節税効果を損ねてしまう可能性もあるため、出口戦略を含めた設計が不可欠です。これからiDeCoを始める方、すでに加入中の方も、制度改正をきっかけに一度立ち止まって、自分に合った活用法を見直してみましょう。
参考文献
- 【アセットマネジメントOne】2025年iDeCo制度改正のポイント
https://www.am-one.co.jp/hagukumu/article/column-20250718-1.html?utm_source=chatgpt.com - 【楽天証券】iDeCo出口戦略と2026年税制改正の影響
https://dc.rakuten-sec.co.jp/about/improvements/?utm_source=chatgpt.com - 【保険の教科書】2025年度税制改正|iDeCoの出口戦略に激震!
https://hoken-kyokasho.com/【2025年度税制改正】idecoの出口戦略に激震!受取時の?utm_source=chatgpt.com - 【ソニー生命】iDeCoの受け取り方・節税の違い
https://www.sonylife.co.jp/simulation/ideco/column/index_07.html?utm_source=chatgpt.com - 【freee】iDeCo改正内容の要点まとめ(2024年版)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/ideco-amendment-2024/?utm_source=chatgpt.com - 【厚生労働省】年金制度改正法(2025年6月成立)
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001365075.pdf?utm_source=chatgpt.com - 【SBI証券】iDeCoの制度・加入条件の詳細解説
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&_ControlID=WPLETmgR001Control&burl=search_i&cat1=ideco&dir=ideco&file=ideco_top.html?utm_source=chatgpt.com

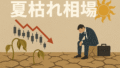

コメント