成長産業に目星をつけて、いざ投資を!と思ってもどの企業の株を買えばいいの?📈
そんな投資フレンズも多いのでは?
わいも個別投資を絶賛勉強中につき一緒に勉強していきましょう。
本日は【EPS】ついて!
モーサテを見ていると、「マイクロソフトの決算においてEPSは予想を上回る結果となりました」等という具合で使われるEPS。
株価と業績のパフォーマンスを計る上で重要な指標で、予想を上回ればなんとなく良さげなんだろうと思いながら聴いていますよね。
わいも同じです。
内容について理解できれば、雰囲気投資家気取れそうなので理解していきたいと思いまっす。
【EPS】
Earnings Per Shareの略で、1株あたりの純利益(当期利益)を意味する指標です。
計算式は「当期純利益 ÷ 発行済株式数」となり、今期の最終的な利益は1株あたりにするといくらになるかということです。
具体的な数字を用いてみると、一年間で1億円の利益をだした企業が発行している株式数が10,000株だった場合、
1億円÷10,000=10,000円になりますな。
これで、企業の収益性や成長性を評価すると共に、配当金額の正当性を見極められます。
前年と比較してEPSが上昇しいれば収益性が高くなっているし、成長が期待できるわけっすな。
しかし、何点か落とし穴もあるので注意!
不動産の売却等、本業とは別の要因で大きく利益が出た場合は「特殊要因」を除いた上での本業の収益性や成長性を分析する必要があります。
また、株式の流通を増やすために実施する「株式分割」により、発行株式数が増えた場合においてはEPSの分母が増えるのでEPSは下がります。
その為、過去のEPSと比較する時は株式分割分を加味して比較する必要があるってことすな。
更に、配当金額の正当性を見極めるためにも重要!
配当金は利益から支払われため、EPSがゲキ低にも関わらず配当金が支払われている企業は、将来的に減配の可能性がある点注意!
利益から何パーセント配当金として支払われるかと言う「配当性向」は、企業の規模やフェーズにもよりますが20%〜50%が一般的とされており、これを超えて配当金を支払っている企業は何かしら無理をしている可能性があるので要注意やで💡
その他、企業単体の分析に留まらず、国全体の経済状況であるファンダメンタルズを計る上でも用いたれたります。
例えば、アメリカの小売り最大手ウォルマートの2014年11月から2025年1月期の決算は、1年前から売上高が4%増え、調整後の1株利益2.41ドルとともに市場予想を上回りました。しかし、2026年1月期通期の見通しについては、調整後の1株利益は市場予想の2.76に対して2.50〜2.60と下回ったことを受けて、ウォルマートの株価は一時、7%を超えて下落!
こんな感じで、米国のGDPにおいて小売が7割を占める中、小売大手のフォルマーとが業績見通しを引き下げてEPS予想を下回れば、今後の米景気減速が示唆されると言う具合っす。
マクロ指標だけで決めるのではなく、ミクロ経済と照らして分析する必要があるなと思う次第です。

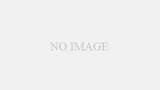
コメント