保険に加入することは、人生のリスクに備える重要な手段のひとつです。特に「積立型生命保険」は、保障と資産形成を両立できる商品として多くの人に勧められています。しかし、その実態をよく調べずに契約してしまうと、長期的に見て「思ったより増えない」「必要な時にお金を引き出せない」「元本割れした」といった後悔を招くリスクがあります。
一見魅力的に見える積立型生命保険ですが、実は資産形成の観点から見ると、非常に非効率である場合が多く、特に若い世代や投資初心者にとっては注意が必要です。
本記事では、積立型生命保険の基本的な仕組みから、その利回りの低さ、資産運用手段としてのデメリット、そして保障と運用を分けるべき理由までをわかりやすく解説します。保険を契約する前に、ぜひこの記事を読んで冷静に判断していただければと思います。
積立型生命保険の基本的な仕組み
積立型生命保険とは、毎月一定額の保険料を支払いながら、死亡保障などの保険機能とあわせて、お金が将来的に戻ってくる「貯蓄機能」を兼ね備えた商品です。代表的な商品には、終身保険、養老保険、学資保険などがあり、いずれも「払ったお金が貯まり、将来返ってくる」といったイメージで販売されています。
この手の保険商品は、特に子育て世代や老後資金を意識し始めた層に向けて「保険と貯金が一体になって便利です」と勧められることが多いです。しかし、その実態をよく見ると、思っているほど利便性が高いわけではなく、注意点がいくつもあります。
まず、積立型保険の保険料には「保障部分」と「貯蓄部分」が混在しており、そのうちの一定割合は保険会社の運用や販売手数料に充てられます。その結果、毎月支払っている保険料すべてが自分の資産になるわけではありません。さらに、加入から数年〜十数年は「解約返戻金」が元本割れするケースも多く、途中で解約すると損をするリスクも高いです。
また、保険会社が運用する商品は、低リスクの国債や債券などが中心となるため、利回りも非常に低く抑えられています。つまり「増える」と思って加入しても、物価上昇(インフレ)にすら追いつかないような利率にとどまる可能性があります。
さらに、加入してから保険の見直しや解約を検討しても、支払った保険料の大半を回収できない期間が続くため、柔軟な資産設計が難しくなるという欠点もあります。特に住宅購入や子どもの教育費など、人生のイベントが重なる30代〜40代にとって、自由に使えないお金が増えることはリスクになりかねません。
このように、積立型生命保険は「長期契約が前提」「自由度が低い」「運用効率が悪い」といった特徴を持っており、その性質を正しく理解せずに加入すると、後悔する可能性が高まります。
なぜ利回りが低くなるのか?
積立型生命保険が「お金が増えにくい」とされる理由の一つが、その利回りの低さです。保険という商品は、単純な投資商品とは異なり、保険会社による運営コスト・死亡保障費用・販売手数料など、多くの費用が差し引かれたうえで資産運用が行われます。
保険会社は主に安全性の高い国債や社債などの債券を中心に運用しています。そのため、リスクが低い代わりにリターンも控えめで、期待できる利回りは年1%未満~せいぜい2%程度にとどまります。これに対し、同じ資金を長期的にインデックスファンドなどで自分で運用すれば、年3%〜7%程度のリターンを期待できるケースもあります。
また、契約初期の数年間は「解約返戻金が元本を下回る」期間が続くのが一般的です。つまり、いったん加入すると一定期間は事実上の“損失確定期間”に入ることになります。もし途中でライフプランの見直しや資金需要が発生した場合、柔軟に資金を動かすことができません。
さらに、インフレが進んだ場合にも不利です。保険の利回りがインフレ率を下回ると、将来受け取るお金の「実質的価値」は目減りしてしまいます。長期にわたって積立を続ける保険だからこそ、物価上昇に弱い構造は無視できないデメリットなのです。
資産運用として不利な理由
積立型生命保険を“資産運用”の手段として選ぶことには、大きな誤解があります。その理由は、「保障」と「運用」が一体化している点にあります。一見すると合理的に見えますが、実際には次のようなリスクをはらんでいます。
まず、積立型保険の大半は長期間の契約が前提です。途中で保険料の支払いをやめたり、満期前に解約したりすると、元本割れが確定します。つまり、ライフステージの変化や予期せぬ出費に柔軟に対応しにくいのです。
また、自由に資産配分を変えられないことも不利な点です。保険会社が運用先を決めているため、時代の変化に応じて株式・債券・金などへの配分を調整する柔軟性は一切ありません。これは、分散投資やリスクコントロールの視点からも不利です。
加えて、複雑な手数料構造も問題視されています。販売手数料、契約維持手数料、保障費用などが保険料に含まれているため、表面上の「返戻率」では実際の運用効率は見えづらくなっています。これは他の投資商品と比較して、透明性が著しく劣る要因です。
保険と投資を分けるべき本当の理由
ここまで見てきたように、積立型生命保険は「保障と資産形成を一度に叶えられる」という触れ込みのわりに、どちらの目的にも中途半端になりがちです。そこで推奨されるのが、「保障」と「運用」を切り離す考え方です。
たとえば、死亡保障が必要な人は、掛け捨て型の定期保険で十分にカバーできます。掛け捨て保険は保険料が安価で、必要な期間だけ保障を受けられるため、支出を最小限に抑えることが可能です。
一方、資産形成はiDeCoやつみたてNISA、インデックス投資といった手段で、自分のライフプランやリスク許容度に合わせて実行するのが理想的です。これにより、運用の自由度が増し、結果として資産が効率よく増えていく可能性が高まります。
つまり、保険は「万一の備え」に集中し、運用は「将来に向けた資産形成」に集中させることで、コスト・リスク・リターンのバランスが最適化されるのです。
番外編:がん保険 3代疾病保険に加入しなくても良い
がん保険や三大疾病保険は重病時の備えとして人気ですが、国の「高額療養費制度」と比較するとコストパフォーマンスが悪い面があります。
この制度では、1か月の医療費が一定額を超えると超過分は公的負担となり、自己負担は年収に応じて抑えられます。たとえば年収500万円程度の方なら、自己負担は月8〜9万円前後にとどまり、さらに高額な医療費が複数月にわたる場合は限度額も軽減されます。
一方、民間保険は毎月保険料を支払い続けても、病気にならなければ給付はゼロ。
仮に給付があっても、高額療養費制度の対象で自己負担が軽く済むため、実際の経済的恩恵は限定的です。
結果として、保険料総額に対して得られるリターンが低くなりがちで、特に貯蓄で医療費に備えられる人にとっては、加入のメリットは薄いといえるでしょう。
まとめ:積立型保険を選ばない判断軸
積立型生命保険は、表面的には魅力的な商品に見えるかもしれません。しかしその実態は、低利回り・高コスト・柔軟性の欠如といった欠点を多く抱えており、特に資産形成を目的とするには不向きです。
「保障」と「運用」は別々に考えることが、ライフプランを自由に設計するうえで非常に重要です。必要な保障は掛け捨て型保険で備え、資産形成は別の金融商品で実践することで、効率的で納得感のあるお金の使い方が可能になります。
人生100年時代を見据えて、今後の資産計画を考えるうえで、「積立型生命保険=正解」という先入観を捨て、冷静な目で商品を見極めていきましょう。
参考文献
- 【FPが本音で語る】積立型保険が「損」と言われる理由|All About
https://allabout.co.jp/gm/gc/490946/ - 保険は本当に必要? 「貯蓄型生命保険」の落とし穴とは|東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/536374 - 積立型生命保険に加入する前に知っておくべきこと|ダイヤモンド・オンライン
https://diamond.jp/articles/-/313054 - 貯蓄型保険と投資信託の違いとは?数字でわかる比較|マネカツ
https://manekatsu.com/magazine/article_detail/1723 - 保険よりも投資?積立型保険が選ばれない理由|楽天証券トウシル
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/35874 - 積立型保険の解約と家計改善の実体験|しさんアップ
https://shisan-up.net/column/saving-life-insurance/
(PR)資産運用するなら【DMM.com証券】!
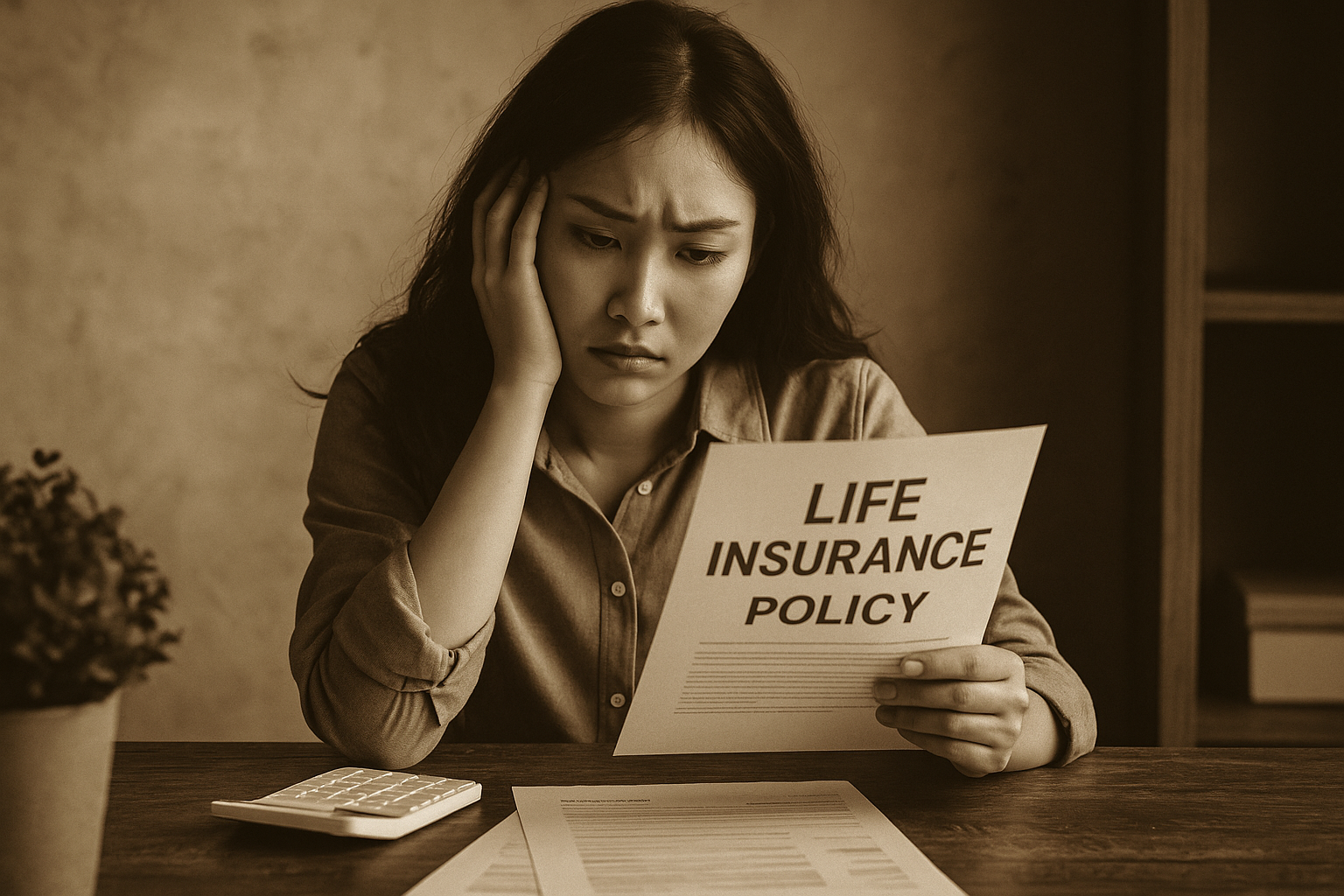


コメント