「エミン流 会社四季報 最強の読み方」から学ぶ
今回も、「エミン流四季報の読み方」を紹介します。
前回は、財務諸表や株価指標で重要視することについてまとめました。
【初心者向け】インデックス投資家 個別株投資について学ぶ「エミン流 会社四季報最強の読み方」その①
今回は、実施に四季報を読んで分析を進める上でのポイントをまとめたいと思います。
会社の特色・事業構成を把握
【特色】の確認(企業の特色や海外事業の内容が書かれている)
【連結事業】の確認
(複数ある事業の、収益構造や収益率を確認する。主要事業(柱)を把握しておく)
記事を読む(業績記事・材料記事)
業績記事で業績動向を確認する
材料記事では資本業務提携、海外進出、株式取得情報などが書かれている
業績と財務を見る
【財務諸表で確認】
・増収増益:今期、来季の業績予想を確認して増収増益であること
・自己資本比率:70%以上が望ましいが、業者や状況を鑑みて50%程度も許容範囲内
(建設や不動産は借金が多い業種、銀行は顧客の預金を貸し出す為自己資本比率が低くなる)
・有利子負債:無借金企業が望ましいが、レバレッジを効かせて事業をする業種は別
・現金同等分:自己資本比率が低くても、現金同等分を確認する
・営業CF:営業キャッシュフローが黒字であることを確認、有利子負債と比較して有利子負債が多すぎないか
バリュエーションをチェック
【予想配当利回り】
長期国債金利が1%弱の市場環境を鑑みれば、国債よりもリスクの高い株の利回りが1%よりも低い場合は、投資対象としては魅力は低い。元本割れしない国債に投資する方が安全かつ収益も高いことになる。
求める利回りは人それぞれだが、長期金利が1%付近で推移している環境であれば、3〜5%くらいが妥当な水準のように思える。
【株価指標】(バリュエーション)
PERやPBRは一般的な見方とは相違はなく、PERは15倍割れ、PBRは1倍割れが割安と考えて良いが、あくまでこれらは企業業績の結果であり、割安には割安なりの理由がある。
割安銘柄は魅力的に感じるが、割安である原因をしっかりと分析することが大切である。
【チャート】
・四季報では、月足チャートが表示されており、大きな流れを確認することができる
・上昇トレンドか下落トレンドかを確認
・ローソク足が移動平均線より上にあるか、移動平均線が下落トレンドなのか
(移動平均線は12ヶ月平均 点線は24ヶ月平均)
時価総額で考える
会社の価値を考える時は時価総額で考えることが大切。
市場規模に対して、過大評価なのか過小評価なのかを確認することができる。
前回のブログで説明したPSR(株価売上高倍率)は時価評価にフォーカスしており、時価総額を売上高で割って求めるもの。
例えば、売上高が1000億円ある企業の時価総額が300億ならば明らかに割安と思える。
【初心者向け】インデックス投資家 個別株投資について学ぶ「エミン流 会社四季報最強の読み方」その① PSRを掘り下げる
【株主総会に参加した場合、質問する3つのこと】
①ビジネスを展開している市場の規模感とシェア
②その市場が10年後どのくらい成長していくのか
③5年後、10年後にどのくらいシェアを獲得しているか
1兆円の市場規模で10%のシェアであれば、売り上げは1000億円である。
そうであるにもかかわらず、時価総額が500億円なら株価は倍になる可能性がある。
更に10年後に市場規模が5兆円まで伸びるとなれば、シェアが10%のままでも売上高は5000億円となり、株価は10倍になる可能性がある。
また、その中でシェアを拡大するポテンシャルがあるならば、更に株価は上昇する可能性がある。
株主総会に参加しなくても、市場規模に対する企業の立ち位置を分析して、今後どのくらい市場規模が大きくなり、シェアを伸ばせるポテンシャルがあるかを分析し、時価総額と比較するだけで株価の割安と割高が見えてくる。
PERやPBRなどの指標と合わせて時価総額と市場規模の見ることで、より精緻に分析することができる。
更に掘り下げる
【社員の平均年齢、平均年収を確認】
インターネットでその企業の社員の平均年齢や、平均年収について確認する。
平均年齢は低い方が良いし、平均年収は高い方が社員のモチベーションも高くなる。
【経営者がホームページに顔出しをしているか
会社の責任者として、しっかりと顔を出して企業を代表しているかは大切。
【株主構成】
①株式の持ち合いがあるか
②オーナー起業家かどうか
③資本提携先
④外国人投資家の持ち株比率
⑤浮動株比率
株式持ち合いについては、持ち合っている会社が保有比率の上位にあれば、今後持ち合い解消の動きが進めば株価を押し下げる要因になる。(昨今、資本効率を意識して持ち合い解消を進める企業が少なくない)資本効率が改善すれば株価上昇につながるが、目先は売り圧力繋がる可能性がある。
グロースや中小企業ではオーナー企業である場合があり、オーナーが株を多く保有していればオーナー自身が株価を引き上げることにインセンティブがある。
一方で、サラリーマン経営陣の場合はオーナー企業ほど株価を引き上げる意識が低いことが多い。
グロース企業の場合、大手企業と提携しているか確認する。
大企業からお墨付きを得ているとの見方もできるし、今後企業買収などで株価が上昇する可能性がある。
外国人投資家の比率が多い方がよい。
海外投資家が興味を持っている企業は何かしらの魅力がある。
浮動株比率は、特定の株主に保有されているものではなく、株式市場で売買されている株式の比率。
浮動比率が低い場合は、重要なことが起きた際に株価が大きく動く可能性がある。
発行株が少なく、浮動株比率が低いと株はより大きく動く可能性が高い。
株式市場の流動性を把握する上で重要。
まとめ
企業の特色や事業構成、業績や財務体質、さらにはバリュエーションや株価チャートに至るまで、複数の視点から多角的に分析することが重要です。PERやPBRといった定量指標だけでなく、時価総額と市場規模の関係、株主構成や経営者の姿勢といった定性面にも目を向けることで、株価の真の価値を見極めることができます。
株式投資は一見複雑に感じるかもしれませんが、ひとつひとつの要素を丁寧に確認することで、リスクを抑えた堅実な投資判断につながります。今回紹介したようなチェックポイントを習慣化し、自分なりの分析軸を持つことが大切です。


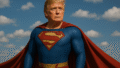
コメント